- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
身体をケアしまくる
2020/11/30
全集中・ヨガの呼吸?!
2020/11/29
もう3歳
2020/11/28
東大生活物語 第十二話「食堂×麻婆豆腐」
2020/11/27
実年齢と身体年齢
2020/11/26
砂上のヨガ
2020/11/24
再び鹿島神宮へ
2020/11/23
新たな日課
2020/11/22
東大生活物語 「うっかり休載」
2020/11/20
ネタ募集中
2020/11/19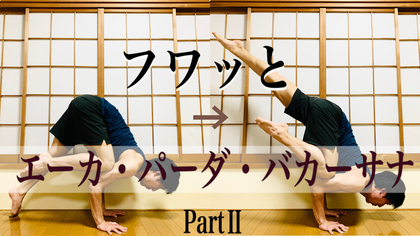
足止め
2020/11/18
YouTubeはじめました
2020/11/17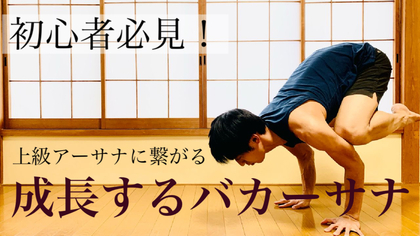
オンライン×頻度×成長
2020/11/15
催眠×解除
2020/11/14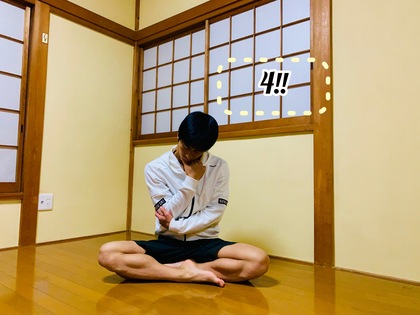
実は人からかけられた催眠は基本的に時間が経てば解けるそうです。
人によって催眠のかかり方は全然違うのでみんなが同じ時間で解けるわけではありませんが、少なくとも授業が終わって講堂から出て行く頃にはほぼ全員が解けているてあろうと言っていました。
しかし稀に催眠状態が長続きしてしまう人がいるので催眠術師はかけた催眠をしっかり解くのがマナーだそうです。
東大生活物語 第十一話「催眠術×忘却術」
2020/11/13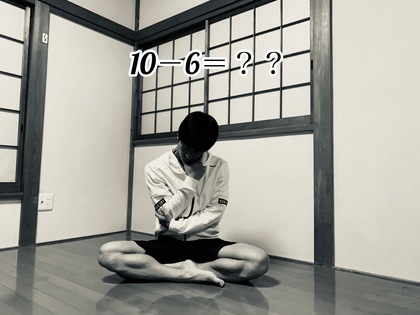
メンズの選択肢
2020/11/11
向上心
2020/11/10
HSP×能力発揮
2020/11/09
HSP=Highly Sensitive Person
2020/11/07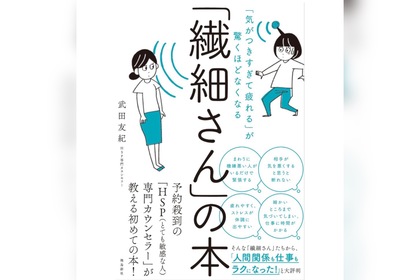
・感覚に強い刺激を受けると容易に圧倒されてしまう
・自分をとりまく環境の微妙な変化によく気づくほうだ
・他人の気分に左右される
・痛みにとても敏感である
・忙しい日々が続くと、ベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ、刺激から逃れられる場所にひきこもりたくなる
・カフェインに敏感に反応する
・明るい光や、強い匂い、ざらざらした布地、サイレンの音などにに圧倒されやすい
・豊かな想像力を持ち、空想に耽りやすい
・騒音に悩まされやすい
・美術や音楽に深く心動かされる
・時々神経が擦り切れたように感じ、一人になりたくなる。
・とても良心的である※1
・すぐにびっくりする(仰天する)
・短期間にたくさんのことをしなければならない時、混乱してしまう
・人が何かで不快な思いをしている時、どうすれば快適になるかすぐに気づく(たとえば電灯の明るさを調節したり、席を替えるなど)
・一度にたくさんのことを頼まれるのがイヤだ
・ミスをしたり物を忘れたりしないよういつも気をつけている。
・暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている
・あまりにもたくさんのことが自分の周りで起こっていると、不快になり神経が高ぶる
・空腹になると、集中できないとか気分が悪くなるといった強い反応が起こる
・生活に変化があると混乱する
・デリケートな香りや味、音、音楽などを好む
・同時に自分の中でたくさんのことが進行すると気分が悪くなる。
・動揺するような状況を避けることを、普段の生活で最優先している
・大きな音や雑然とした状況など強い刺激に悩まされる。
・仕事をする時、競争させられたり、観察されていると、緊張し、いつもの実力を発揮できなくなる
・子供のころ、親や教師は自分のことを「敏感だ」とか「内気だ」と思っていたBL眼鏡とマスク
2020/11/07
東大生活物語 第十話「心理学×催眠術」
2020/11/06
ブルーライト
2020/11/05
運動会×玉入れ
2020/11/04
高弟は見た!Ep.1「インストラクションの妙」
2020/11/03
お初にお目にかかります。
僕はRSYのエース、そしてヨガ界のプリンスとも言われ、このブログに度々登場してきましたS君であります。
前々からひしひしとバイブスは感じていたのですが、皆さまからの熱い声援に応え、本日、ついに筆を取った次第です。
これからは高弟である僕から見た相島先生を少しずつ書いていくシリーズ「高弟は見た!」を気まぐれで連載したいと思います。
皆様は相島先生にどのような印象を持たれているでしょうか?
きっと優しくて、かっこよくて、頭も良い、もちろん筋肉もすごい、でも茶目っ気もあって、誠実で丁寧なレッスンをしてくれる、そんな感じではないでしょうか。
そのことに関しては高弟である僕も全く異論はありません。しかし、レッスンを受けたり、ブログを読んでらっしゃる方は薄々、いやもうすでにかなりお気付きだと思いますが、師匠はかなりの変わり者です。
元々友達だった師匠と僕は、去年の夏、一緒にあるライブに行きました。過去のブログにあるフリスビーを取ったライブです。(フリスビーのち鍵〜その1〜、フリスビーのち鍵〜その2〜)
そのフリスビーを待つ時、師匠は僕にこう言いました。
「こういう時のために、普段アナ骨とかで鍛えてるんだ!」
「師匠はフリスビーを取るために鍛えてるんだ…。」と心の中で驚きの声が響きましたが、
なぜか僕の士気はぐんと上がりました。
わけの分からない発言でも士気を上げてしまう、師匠のインストラクションの凄みを感じた瞬間でした。
エッセンシャル思考
2020/11/02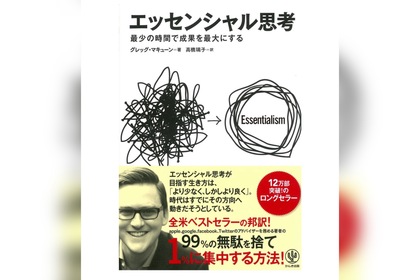
渋谷
2020/11/01
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以














