- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
一番の歓声
2019/08/31
今朝もいつも通りアナトミック骨盤ヨガがありました。毎回レッスン内での参加者全体のテンションの上がり下がりというのはあるのですが、今日のレッスンで一番盛り上がったところは僕が活躍した部分ではなく参加者のTさんが活躍した瞬間でした。
アナ骨では身体の内側から熱が起きるので一連の動きをした後は下半身がとてもストレッチしやすい状態になっています。なのでいつもクールダウンタイムには数分間自由にストレッチをする時間を設けています。前屈や腿前伸ばし、鳩のポーズや開脚系の動きなどから自分で選んで柔軟性を高めています。
前述のTさんはだいたい毎週アナトミック骨盤ヨガに参加している女性なのですが、最後の時間には毎回前後開脚を練習しています。最初の頃は前後開脚をしてみるもののヒザがまっすぐには伸びずお尻ももちろん床から高く浮いた状態でした。でもここ数週間は柔軟性が飛躍的に上がり毎週来る度にお尻の位置が床に近づいていきました。他の参加者からも目に見えるほどの変化だったので「成長がすごい!」という声が毎回上がっていました。
そして今日ついに、
お尻が床について脚が前後にきれいに伸びた状態に!
その瞬間ドッと歓声が沸き拍手が起きました。
なぜかクラス内がまとまった瞬間。いやぁ、僕が話している時やアーサナしている時なんかはそんなに盛り上がることはないんですけどね^^;人の成長には力がありますね。
家でもストレッチをやり込んでいるのか聞いてみると週一のこのレッスンだけしかやっていないそう。やはりBefore Afterの写真撮らせてもらっておけば良かった…(Afterはこの先撮れますがBeforeはリバウンド(?)しない限りは撮れないですからね。)そういうところはマメじゃないんですよね^^;
そんなわけで写真はないので骨格標本キャリボンの前後開脚写真で失礼します。
水道管破裂
2019/08/30
タイトルの通り昨日家の水道管が壊れました。(破裂って感じではなくパーツがポーンと外れた感じと修理屋さんは言っていました。)
僕は水泳の仕事で家を離れていたので現場には居合わせなかったのですが、妻の話では家の横側が洪水のようになっていたそうです。近所の方が気づいて教えてくれたようでした。その方のアドバイスですぐに家の水道の元栓を閉め洪水は収まったのですが、もちろん家中の水道は使えない状態です。
そんなこんなで僕も家に到着し修理屋さんを呼んで応急処置が終わるまで待っていたのです。でもふとした瞬間に何度か蛇口を手を伸ばし水を出そうとしてしまいました。でも当然水は出ない。蛇口をひねれば水が当たり前のように出る、その感覚がいかに日本では染みついているかがわかりました。大地震で水道も電気も止まったら本当に大変なんだろうなと思います。保存のきくペットボトルの水なんかをを備蓄した方がいいですね。
数時間水は止まったままでしたが無事に応急処置も終わり、ちゃんとした修理は一週間後くらいになるそうです。経年劣化が進んでいる家は今日本にはたくさんあるようです。水道料金もちゃんとチェックした方がいいかもしれませんね。
以上水のトラブルのお話でした。
ドルフィン
2019/08/29
数日前のブログで「夏の終わり」なんて言っていましたが暑さ復活ですね。木曜日は移動も多いので汗が止まりません…また熱中症気味にならないよう気をつけないといけません。
ここのところヘッドスタンドについて書いていましたが、「逆転のアーサナはちょっと怖くて…」という方も多いはず。今日はそんな方でも安心してヘッドスタンドの力をつけられるドルフィンポーズを紹介します。
方法はダウンドッグを行いそのままヒジを床につけるというシンプルなものですが、主に肩の可動域と股関節の可動域を増やします。また体幹力の強化が期待できます。ヘッドスタンドをする時に肘で床を押せない、という方にもおすすめです。
ポイントは、
・ダウンドッグと同様に腰を伸ばしたまま股関節の屈曲をしっかり行う。(腸腰筋を使う。)
・背中は反りすぎないようにしながら肩の位置を床に近づける。
・床に置いているヒジは手よりも広げない。
・ヒジで床を強く押す。
ダウンドッグに比べて肩周りの筋力や柔軟性がより必要となります。最初は肩と股関節が思うように動かないかもしれませんが、ヘッドスタンドやピンチャ・マユーラアーサナ(肘倒立)の為の身体作りに生かしてみてくださいね。
水泳をやっている方はドルフィンキックの改善にも役立ちますよ。(シャレじゃなくて本当に!)
ヘッドスタンドの補足
2019/08/28
一昨日のブログでは動画付きでヘッドスタンドの説明をしましたが一つ大事なことを書き忘れてしまったのでここで補足しておきます。
いつかのブログ視点(ドリスティ)でも説明しましたが視点を定めることで身体全体が安定します。特にバランス系のアーサナでは一点を見つめることがとても大事になります。片足立ちのアーサナで目が泳いでバランスを崩してしまった経験のある方も多いのではないでしょうか。ヘッドスタンドなどの逆転のアーサナではなおさらその影響が出ます。
ヘッドスタンドを安定させるにはもちろん体幹力などは必要なのですが、もう一つ大事なのは
視点を定めること。
ヘッドスタンドの時の視点ですが、最初のうちのおすすめはマットの上の一点。それも頭から近い位置の方が集中しやすいように思います。ともかく一点に定めて集中力を高めます。アシュタンガヨガのヘッドスタンドでは鼻先に視点を定めますが、慣れないうちは難しいと思います。
ヘッドスタンドがどうも安定しない方、目を向けやすい位置を見つけてトライしてみてください。
夏の終わり
2019/08/27
ここ何日かはだんだんと夏の終わりに近づいているのを感じます。毎朝5時半頃に起きてヨガをしてるわけですが、今日なんかは窓を開けていると肌寒さすら感じました。夜も涼しいことが多いですね。
今年は7月前半が雨ばかりで寒かったのもあって特に夏が短く感じます。猛暑日が続く時があったりで体力も落とすこともあったけれど、いざ夏の終わりの雰囲気を感じ始めると本当に夏らしい夏は一瞬だったなと思い寂しさも感じます。
過ぎてみれば一瞬というのは夏以外にも当てはまることで、よく四季が人の一生にたとえられますが、人生というのも過ぎてみればあっという間なのでしょう。その点ではこの夏の長さも人生の長さも大差がないのかもしれません。
違うのは人生の方はまだ過ぎ去っていないということ。過ぎ去ってしまった夏とは違い様々な意味でのチャンスが転がっています。
またもう一つ違う点は人生の方はいつ終わるのかの予想がなかなかつかないこと。50年後か10年後か明日か。短い夏よりも人生の方が長い保証なんてないのですね。一夏を楽しむよりも人生を楽しみ切る方が難しいことだってあるのです。
季節が終わりを告げる度に時間の速さを感じます。仕事でも日常のことでも終わりを目指して頑張るのですが終わってみるとその過程は儚いもの。
いつでも「今」「ここ」に集中していたいものです。
なんだか夏が過ぎ去った前提の内容になってしまいましたが、まだまだ暑い日は続くようです。熱中症などにはくれぐれもお気をつけください。
僕はといえば朝から頭の中を森山直太朗の「夏の終わり」がエンドレスで流れています。みなさんもエンドレスリピート機能にはお気をつけください(笑)
ヘッドスタンド
シールシャアーサナ
2019/08/26
昨日のHIP JOY YOGAは欠席が多く少人数だったため急遽予定を変更して「ヘッドスタンド(頭立ち)」練習クラスにしました。ヘッドスタンドとは文字通り頭を床につけて脚を上に持ち上げる逆転のポーズの一種です。
昨日のクラスではまずヘッドスタンドでは主に体のどこを使うのかを分析して、その部位を他のアーサナを用いて活性化させました。しっかり体が使いやすくなったところで実際のヘッドスタンドの練習へ移行しました。
大事なポイントとしては、
・腕と頭でつくる土台の形
・肩甲骨からヒジを押す力(前鋸筋)
・前屈(脚裏の柔軟性)
・身体後面の力(お尻や腿裏、背中)
・動きを安定させるお腹の力(腹横筋・腹直筋)
まずはしっかりと土台の形をつくることが大事です。前腕や肘で床を押さないと頭に体重がかかり過ぎて頚椎に負担がかかってしまいます。頭と肘先全体に均等に体重がかかるように調整しましょう。
シールシャアーサナはアーサナの王様とも呼ばれ体幹力強化や集中力アップなど様々な効果がありますが、慣れていないうちは転倒の危険もあります。自宅で練習する場合は布団などのクッション性のあるものを敷いたり補助を頼んだりしながら自己責任で練習しましょう。
最初は膝を曲げた状態のキープまでで十分ですのでゆっくりと感覚を覚えていってください。
熱量
2019/08/25
昨日から今日の午前にかけて息子の幼稚園でのお泊りイベントでした。キャンプファイヤーや花火、かき氷と夏らしさ満載の2日間。息子も一つたくましくなった気がします。
そのため昨日のブログは適当になったわけですが、今日は「熱量」についての話です。
「その物事に対してどれだけのエネルギーを注げるか?」ということなのですが、目の前のことに完全に集中して自分の力を発揮するというのはなかなか難しいことかもしれません。
ヨガの実践はこの熱量を上げる作用があると強く感じています。僕自身毎朝1時間半ほどアシュタンガヨガを行っていますが、日々繰り返していく毎にまずはヨガに対するエネルギーの注ぎ方や集中力が上がってきています。そうするとヨガ以外のことに対して注げる熱量も上がってくるのです。
熱量の高さ=生命力の高さと捉えることもできるかもしれません。生命力自体はやはり先天的なものが大きいとは思うのですが、ヨガには身体能力を上げるだけでなく、生命力そのものを上げる力があるように感じます。結局身体を鍛えるという手段にはなるのですが、単なる筋トレというよりも呼吸や全身の統合といったエッセンスが入ってくると良いように思います。(単なる筋トレでも効果はありますが。)
もちろん生きがいや目標や夢を持つこと自体が大きな原動力になり高い熱量を生み出します。精神から身体への影響は計り知れません。ただしある一定の熱量がそもそもないと自分が熱を注ぎ込めるものすらみつからなかったりします。その場合はヨガで身体を鍛え整えてみる。すると身体から精神への繋がりでなんだかやる気が出て本当にやりたいことが見つかるかもしれません。
色々なアプローチ方法があるのだとは思いますが、「熱量」や「生命力」といったものは人生を彩らせる起爆剤のようなものなのではないでしょうか。
ところで今回の写真は内容とは全然関係がないもので、外を歩いている時に「もうすぐ秋だなぁ」と感じたので撮ってみたものです。
熱量低めブログ
2019/08/24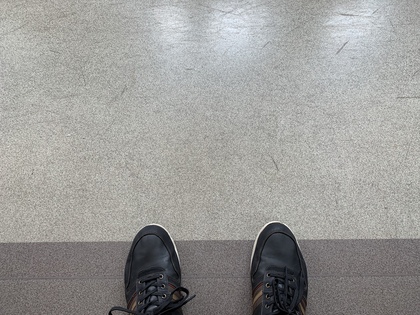
昨日のヨガ講座では「熱量」の話も出ました。ここでいう熱量はカロリーとかではなくて「物事に対して自分の力(もしくは時間などの財産)をどれだけ注げるか」というもの。この熱量に関しては僕も日々意識していて自分自身のヨガのテーマの一つでもあります。
ブログに関してもやはり熱量を増やしていきたい、という想いはあるのですが、今日は熱量をグッと下げて明日に回してしまいます(笑)
今日は午後から幼稚園のお泊まり行事でスマホをいじってブログを書く時間が本当になさそうなのです。ですので一応「書いた」という証拠だけここに残して、また明日改めて「熱量」については書こうと思います。
調布から飛田給間の3分で書き終えて写真も適当な「電車でブログを書いている自分の靴」のもので失礼しますm(_ _)m
疾患とヨガ
2019/08/23
今朝のアナトミック骨盤ヨガはいつもご参加いただいている方には申し訳ないですがお休みにさせていただきまして、その時間を使ってアナトミック骨盤ヨガの内田かつのり先生のヨガ講座に参加してきました。
テーマは「5つの疾患とヨガ」。今日取り扱った5つの疾患とは、
五十肩
椎間板ヘルニア
坐骨神経痛
変形性膝関節症
胸郭出口症候群
(正確に言えば「坐骨神経痛」は疾患ではなく症状の名前ですが。)
RSYのクラスに来られる方の中にも上にあげた疾患に心当たりがある方もいるのではないでしょうか。
疾患の特性を理解した上でヨガでどんなアプローチできるのか、そんな内容の講座でとても勉強になりました。同じ名前の疾患の診断がおりていても人によってアプローチの方法が変わってきます。最終的にはいかにその人自身を診るのかが大切になってくるのだと思います。
医療の力が及ばないところでもヨガによるアプローチが有効なこともあります。(もちろんその逆もまたあります。)講座を通じてインストラクターと参加者、双方での見極めが大切だと改めて感じました。
RSYのクラスにもどんどん生かしていこうと思います。
アーサナメモ・番外編
ジャンプイン
2019/08/22
今日はアーサナメモの番外編として昨日のブログで触れたジャンプインを紹介します。太陽礼拝のダウンドッグから手と手の間へ両足同時にジャンプして着地する動作となります。
手順としては、
1. ダウンドッグの最後の吐く息で膝を曲げてお尻を後ろに引きジャンプするための準備の態勢になる。
2. 息を吸い始めると同時に両足で床を蹴りお尻を高い位置に保ちながら手と手の間に着地する。跳んでから着地するまで途切れさせずに息を吸い続けます。
まあ書いてみると簡単な動作に思えますが、静かに着地するのには練習が必要です。何はともあれまずは跳んでみる。
最初はお尻の位置が低くドスンと着地してしまうかもしれません(動画0:00~)。
次の段階では膝をあまり曲げずにお尻を高く保ったまま着地します。慣れてないと前のめりになって転倒しそうになりますが、ブレーキをかける力をつけていくには恐れずにお尻を高く保って練習します。(動画0:07~)
お尻の位置に慣れてきたらダウンドッグの最後の吐く息のところで骨盤底筋とお腹(腹横筋)を強めに締めます。その引き締めを緩めないまま息を吸ってジャンプ動作に入る。うまくいくとお尻がフワッと浮き、重力を感じさせないような動作ができてきます。(動画0:15~)
さらに慣れたら着地することを途中でやめて戻ってみたりします笑(動画0:25~)
主に必要な要素
・もも裏の柔軟性
・骨盤底筋と腹横筋を引き締め続ける力(ムーラバンダ、ウディヤナバンダ)
・着地でブレーキをかけるための力としては、
ー三角筋前部の筋力
ー前鋸筋の筋力(脇の下)
ー上腕三頭筋
ー手首の強さと柔軟性
上記のように満遍なく様々な要素が必要になってきます。一瞬の動きの中でも複雑な力が働いているのですね。個々の力は太陽礼拝に含まれるアーサナなどで鍛えていき、材料がある程度揃ったら実際に跳んでみてそれらを統合する練習をします。
焦らずに一つ一つ練習してみてくださいね。
ジャンプイン
2019/08/21
今朝のRoot Yoga Moveはお休みの方が多く、少人数でのクラスでした。なので割と自由な内容で進めていき、最初のワークでも普段あまりやらないジャンプインを練習しました。
ジャンプインとは太陽礼拝でダウンドッグからアルダ・ウッターナアーサナへ移行する際に片足ずつ手と手の間に歩いていくのではなく、両足同時に床を蹴ってジャンプし両手の間に着地するというもの。音なく静かに着地するようになるにはけっこうな練習が必要となります。
最初はお尻が下がってしまいドスンと地面に落ちてしまうのですが、慣れてくると肩や脇の下やお腹の力でブレーキをかけてゆっくりと着地できるようになります。今日の練習でもジャンプインが初めての方はどうしても勢いで行くしかないのですが、だんだんと勢いを弱める力もついていくと思います。
その為に有効なアーサナの一つはバカアーサナ。股関節を曲げる力やお腹の力だけでなく肩の前側や脇の下の力もつけることができます。バカアーサナを長くキープできるようになる頃にはジャンプインでのブレーキの感覚もつかめるようになってくると思います。
ところでジャンプイン、ジャンプインと言っても動きの想像ができない方もいらっしゃると思いますので明日あたりのブログで映像付きで解説しようかなと思います。たぶん…時間があればですが。(時間はある、ないではなく自ら「作り出せ」って感じですね^^;頑張ります。)
筋肉痛
2019/08/20
今日はお尻ともも裏と背中がけっこうな筋肉痛で歩くのも辛いです。昨日の朝にピンチャ・マユーラアーサナ(肘倒立)から後屈をして足を頭に近づけていく練習を何回もしたからです。(写真はだいぶ前の使い回しのものですが、今はもう少し足と頭が近づくようになりました^ ^)
筋肉痛になると羨ましくなるのは筋肉痛が大好きな人。RSYのクラスに参加してくれている人の中にもとにかく筋肉痛が好きな人が何人かいらっしゃいます。トレーニングをしてるときだけじゃなく翌日や翌々日も筋肉痛で楽しめるなんて良いことだらけではないかと思います。運動をするモチベーションにもなります。
僕はというと治りかけの筋肉痛は不思議と気持ちよく感じて好きです。でも今日の状態のような一番ひどい時の筋肉痛はまだ良さがわかりません。
いつか全体を通して筋肉痛を愛せる日がくるよう日々努力し続けようと思います(笑)
フリスビーのち鍵〜その2〜
2019/08/19
前回の続きです。
楽しかったライブが終わり、帰り道の途中で一緒に行った友達とも別れ、23時過ぎに京王よみうりランド駅に降り立ちました。駅までは自転車で来ていたため自転車置き場に向かい精算機でロックを解除。自分の自転車の前まで行き、「さあ帰ろう」とリュックサックのポケットに手を突っ込み自転車の鍵を探ると、、
あれ??
鍵がない...
落ち着いてもう一度違う所も探してみよう...
やっぱりない!!!
どこかで自転車の鍵を落としてしまったようです。。スペアキーがあるなら一度歩いて家に帰るところですが数年前に失くしてしまっていました。(本当はその時点でもう一つスペアキーを作るべきだったのですが。。)ともかく自転車を駅に置きっぱなしにしておくことも出来ないので、鍵がかかったまま押して帰ることにしました。
問題はその自転車が電動自転車だということ。持っている人ならわかると思いますが、電動自転車は普通の自転車より圧倒的に重いのです。ロックされていて動かない後輪を手で持って浮かせながら前輪だけ地面を転がして押していきました。簡単そうに聞こえますがやってみるとこれがめちゃくちゃ大変で、10mくらい進めると腕が限界を迎え後輪を下ろしてしまいます。そんな感じで10m進んでは休憩、頑張って15m進んでは休憩、と繰り返しながらゆっくりと家に向かいました。
一昨日は夜になっても気温が高く、高重量の自転車の負荷をかけ続けたので日中のライブでかいた汗の比じゃない量の汗をかきました。その上後輪を持ち上げながら進んでは止まる姿を通行人にチラチラと見られ続ける始末。なかなか距離が進まないもどかしさに「上腕三頭筋だけじゃなくて二頭筋ももう少し鍛えておけば良かった」「筋持久力がまだまだ足りないな」「これはフリスビーをとった帳尻合わせなのか??」などと考えながら頑張り、なんとか家にたどり着きました。自転車に乗れば3分で着く距離、かかった時間はなんと35分!!日付をまたいでいました。。
とりあえず家にはたどり着けたものの鍵のない自転車をどうしたものか。調べてみても鍵番号がわからないのでスペアキーを新たに作ることができず、充電器ごと一式で交換するとしたら相当な費用がかかります。もう自転車自体が古いので自転車屋さんには新車への買い替えを勧められましたが、いずれにしてもけっこうなお金が飛んでいきそうです。フリスビーのように。
もし電動自転車のスペアキーを1個も持っていない人がいましたら明日中に作りに行くことをおすすめします。
フリスビーのち鍵〜その1〜
2019/08/18
昨日の午後は仕事の休みも取り昔から好きなバンドのライブに行ってきました。場所は埼玉のメットライフドーム。ドームと言えど壁で覆われているわけではなく吹き抜けになっていて空調はなし。台風が過ぎた後の猛暑日で全身から汗が吹き出します。でもライブが始まってしまえばそんなことはどうでもよく、むしろ外の夕陽が見えたり気持ちのいい会場でもありました。選曲も自分の一番好きな曲があったり昔の懐かしい曲があったりですごく楽しいライブでした。
そして全曲目が終わり、エンディングではバンドのメンバーがパレードの車みたいなものに乗ってフリスビーを客席に投げながら会場を移動していました。今回僕はスタンド席の中では3列目とかなり前の方だったので「もしかしたらフリスビー飛んでくるかも…?」と期待。いよいよメンバーを乗せた車も自分の席の方に近づいてきました。
どこに飛んできてもキャッチできるようにお尻の筋肉を戦闘態勢にして身構えていましたが、フリスビーはアリーナ席の方へ飛んで行ったりスタンド席に来てもだいぶ遠くに着地したりしていました。そうこうしながらメンバーを乗せた車は僕達の席の前を通り過ぎて行きました。「もうダメかな…」と半ば諦めていると、その車に乗っていた一人、バンドのサポートミュージシャン(キーボーディスト)の方がこちら方向にフリスビーを構えて、、そして、
投げた!
そして斜め右前方の席の人の伸ばした手に弾かれて、
僕の胸のど真ん中に吸い込まれるようにキャッチ!!
とれました!
それはもう本当にベストな位置に飛んできました。嬉しかったです。会場には3万人の人がいますからけっこうな確率です。なんだか最近ツイてます。しかもフリスビーは息子たちが遊ぶのにはもってこいのもの。我が家では実用的なものなのです。
ライブも良かったのに最後の最後にオマケまでついてとても良い気分で帰途につきました。
…その後に起こる出来事のことなど想像だにせず。。
補助輪
2019/08/17
昨日は自転車の話でしたが、自転車の補助輪には考えさせられるものがあります。自転車の補助輪が必要かどうかは年齢や状況によってだいぶ変わるのですが、無くて大丈夫な場合には無くて良いものだと思います。
補助輪があることで自転車自身に慣れて成長を促すのであれば補助輪はすごく有効なものになります。でもある程度すでに自転車に乗れそうな力があるのに補助輪に頼ってそれに慣れてしまっては成長を妨げてしまいます。
自転車に限った場合であれば遅かれ早かれ小学生くらいになればみんな乗れるようになるので補助輪があろうがなかろうが結果的にはあまり関係がないのですが、これが自転車以外のことだとけっこう大きな影響を人生に与えるように思います。
仕事や育児、もしくは病気や身体の悩みなどにおいての補助輪(もちろん比喩としての。)が必要かどうか、自分の今の状況を踏まえての見極めはとても難しいと思います。でもこの見極めができたらグッと人としての成長ができるようにも思います。アナ骨のローランジで手を離していくかどうかもマットの上に単純化された補助輪の話なのかもしれませんね。
頼るべきものと自立のバランス、ヨガはこの辺の見極めの力も不思議とつけていくようにも感じます。
自転車
2019/08/16
今朝は日課のアシュタンガヨガはお休み。なぜかというと長男(3歳)の自転車の練習に付き合うことになったからです。
昨日なんと思いがけず知り合いから16インチの自転車をいただき、息子は初めての自転車を手にしました。今まではストライダーというペダル無しの足で地面を蹴って進むタイプのものに乗って遊んでいました。でも最近はだんだん自転車への憧れも出てきたようで「誕生日に自転車か恐竜がほしい」などと言っていました。(生きた恐竜は難しい話ですが…)
そんなタイミングで自転車をいただくことができたので嬉しさが爆発、まだ猫とカラスしか起きていない早朝から練習を開始しました。
でもペダルをこぐ本物の自転車(補助輪無し!)はなかなかむずかしくコントロールがきかない。僕が補助してもグラグラして横に体重が傾き転倒しそうになります。でも息子は体を動かすのは割と得意。(そして仮にも僕は身体を扱うインストラクター。)1時間ほど練習すると一人でなんとかバランスをとって乗れるようになりました。そして一度コツをつかむと補助はもう必要なくなり一人でスイスイこげるように。
でも思い返してみると僕自身補助輪無しの自転車を練習して乗れるようになったのが確か小学一年生の頃だったような気がします。息子の方が3年も早い…!まあ昔はストライダーなんて便利な物なかったですからね。。(という言い訳)
嬉しさと若干の悔しさを感じた朝でした。
塩麹
2019/08/15
今日もゲリラ豪雨のような雨が降ったり止んだりしています。移動の多い日ですが、今のところ強い雨には当たらずに済んでいます。
さて、昨日は味噌の話でしたが、今日は発酵食品ついでに塩麹です。塩麹は味噌と同じように発酵の力で栄養分が吸収しやすい形に分解されています。さらに塩麹に肉や魚などを漬けておくと酵素の働きでたんぱく質の一部が分解されて柔らかくなります。パイナップルみたいで便利ですね。
味はというと好みが分かれるところだと思いますが、僕は好きです。風邪を引いて食欲がない時でも塩麹のしょっぱさは食欲を増します。鍋などに入れてもいいですね。割と何にでも合うように思います。なんだか最近塩分の話ばかりですね。
我が家ではたまに米麹(写真)を買ってきて塩麹を作っています。作り方は簡単で米麹200g、塩60g、水300mlを混ぜて60℃に保って6〜7時間待てば完成。温度管理が便利なヨーグルトメーカーがあればボタンを押すだけで出来てしまいます。炊飯器で作る方もいるようです。
使う麹や塩の種類によっても味がずいぶん変わりますので色々と試してみてくださいね。
味噌
2019/08/14
今日は朝から雨が降ったり止んだりおかしな天気です。朝のレッスンが終わってスタジオを出ようという時にも急に土砂降りの雨が降ってきました。(駐輪場の自転車はびしょ濡れです…)台風の影響はすごいですね。
今日はタイトルの通り味噌についてです。味噌は特に汗をかきやすく内臓も冷えやすい今の季節に役立つ食べ物です。先週僕は熱中症気味になった時、味噌汁を飲んでだいぶ体が楽になりました。(経口補水液など他の手段との比較はできませんが。)感覚的には味噌はとても体に優しい気がします。
味噌は米や大豆や塩を使った発酵食品ですが、発酵することでもとの原料が細かく分解され吸収されやすい形になります。たんぱく質はアミノ酸となり、炭水化物はブドウ糖へと分解されます。なので熱中症や夏バテで胃腸が弱っていても体に負担をかけず栄養分を吸収できるのです。またビタミンやミネラル類も豊富に含まれているそうです。さらに味噌に含まれる塩は体を温める作用もあり冷え性や低血圧の改善にも役立ちます。
今朝レッスンに来ていた女性は自宅で味噌を作っているそうです。自家製のものは美味しいですよね。
体質に合わせて味噌のパワーをうまく利用してみてください。
アーサナメモvol.10
アドー・ムカ・シュヴァーナアーサナ
2019/08/13

今日は10回目のアーサナメモ。RSYのクラスでも他のどのヨガ教室でも行う頻度の最も高いと思われるアドー・ムカ・シュヴァーナアーサナ(下を向いた犬のポーズ)、通称「ダウンドッグ」です。
たまに「ダウンロック」だと思っている方がいらっしゃいますが、それだと「下を向いた岩のポーズ」になってしまいます。岩のようにじっとしているのでイメージ的には間違ってはいないですが。まあ"d"と"r"の発音は似ているのでしょうがないですね。僕もはっきり言えるよう気をつけます。
このダウンドッグ、太陽礼拝では前回紹介した
ウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ(通称「アップドッグ」)の次に来ます。一呼吸一動作のアーサナの流れの中で唯一5呼吸ほど流れを止めてキープする特殊なアーサナでもあります。じっくりと時間をかけて深めていきたい箇所となります。メモ
・何よりもまず腰を丸めずに股関節から体を折ること。立っている時の自然な腰椎の弯曲を保つ。
・もも裏が伸びず腰が丸まるようだったら膝を少し曲げて緩める。かかとも床から浮かせて調整する。でもだんだんと膝はまっすぐ、かかとは床に着くように。
・肩は外回しにして肩と耳の間にスペースをつくる。
・手の中指は前に向けて掌全体を床に吸い付かせるように置く。
・尾骨を斜め後ろの天井方向に引いて体重を後ろに乗せていく。
・背骨は丸まらせず、反り過ぎずまっすぐな状態を保つ。
・余裕があれば骨盤底筋の引き締め(7割程度の力)とお腹の引き締め(おへそを背骨側に寄せる力)を行いながら肋骨周りを強く使った呼吸をする。
ダウンドッグは基本中の基本のアーサナでありながらも身体の使い方が意外と難しいものの一つです。またムーラ・バンダとウディヤナ・バンダを練習するのにも最適なアーサナでもあります。ダウンドッグの時の骨盤底やお腹の使い方次第で次の動作(一歩で足を手と手の間に置いたりジャンプインしたり)の質も変わってきます。
教室では毎回行いますので上の点を意識して変化を楽しんでみてください。
ところで犬は実際にダウンドッグやアップドッグのようなポーズをとるのでしょうか…?(家に犬がいないのでわからない…)
川遊び
2019/08/12
台風が近づいていますね。その影響で海の事故も増えているようです。海に出かける際には十分お気をつけください。というか台風が近くにある時は行かない方がいいです。競泳経験者でも溺れます。
ところで今日は夏休みらしい過ごし方をしました。家族+おじいちゃんおばあちゃんで川遊びに行ってきました。檜原村辺りの涼しい渓流を目指して出発したのですが、なんだかんだあってそこまでは行かず福生市内の多摩川の河原に降り立ちました。
太陽が雲に隠れるとちょうど良い気候でしたが日が出ると恐ろしい暑さ。また熱中症になってしまわないように今回は水分補給を意識しました。
子供達は岸近くの浅い所でジャブジャブ水遊び、僕は久々に釣りをしていました。川底の石にはたくさんの川虫(ざざ虫=カワゲラの幼虫)がついていたので、それを餌にしてみました。そういえばこのざざ虫をお酒のつまみに食べる地域もあるみたいですね。どこかの道の駅で売っていたのを見たことがあります。なかなか食べる勇気は出ないですが…
そしてざざ虫を餌に釣れたのはオイカワのメス2匹(写真上)とウグイ1匹(写真下)の3匹だけ。本当は渓流に行って山女魚や岩魚を釣りたかったですが、子供達が喜んでくれたので良かったかなと思います。
河原には他にもトンボやバッタなどの虫がたくさんいて子供には恰好の遊び場でした。中でも河原の石と全く同じ色をしたバッタは家の近くでは見ることがないので新鮮でした。
それにしても最近はどんどん日焼けしていきます。一夏でどこまで黒くなるのでしょうか。濃いめの食パンの耳くらいで抑えられるといいのですが。。
𩸽
2019/08/11
昨日の夕飯は𩸽でした。うちの長男(3歳)は𩸽がおいしかったようでまるまる半身分食べきってしまいました。
その後息子は𩸽の元の姿が気になったようで魚図鑑でその全体像を調べていました。「こんな魚なのか。」と納得してついでに他の魚(オオカミウオなど)も調べてあーでもないこーでもないと色々学んでいたようです。
今の時代、魚や肉なども切り身になってスーパーで売っているので、大人でも自分たちが口にするものの元の姿を知らないことがあります。まあ別に知らなくても生きていけるのですが、小さい子供のような興味や好奇心というのは人生を少し色濃くするものではないかなと思ったりもします。自分としては息子を見習いつついつまでもそういったものを失くさないようにしたいなと思いました。
あ、ところで「𩸽」は「ほっけ」と読みます。読めなかった場合の参考までに笑
追記:上の文章やタイトルには「ほっけ」の漢字(魚へんに花)がたくさん登場するのですが、一部のスマホや携帯ではその漢字が表示されないようです。もし表示されない場合には文章の不自然な所に「ほっけ」の漢字があるように想像しながらお読みください。
アーサナメモvol.9
ウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ
2019/08/10

今日はアーサナメモ第9弾。この前の水曜夜のグループワークでも練習したウールドヴァ・ムカ・シュヴァーナアーサナ(上を向いた犬のポーズ)、通称「アップドッグ」です。
太陽礼拝では前回のチャトゥランガ・ダンダアーサナの次に登場します。後屈の一種で太陽礼拝の中でも難易度が高いかなと思うアーサナです。でもポイントをおさえて練習していけば爽快さを感じられるようになると思います。焦らず続けていきましょう。
メモ
・チャトゥランガから移行する際には背中を丸めながら(腹筋を使いながら)徐々に床を押して肘をまっすぐにしてくと股関節の伸展もしやすくなる。
・腰に負担をかけないためには恥骨を前方に押し出すように意識しお腹の力を完全に抜かないようにする。(骨盤を後傾させる時の力)
・肩甲骨は背中側で寄せるようにして胸の中心を天井に向けるようにする。
・肩は耳との距離を保ちすくめないようにする。(肩甲骨の位置を下げる)
・肩は手首の真上に位置します。
・首は胸を反ってから最後に反り目線を上げる。
・床につくのは手の平と足の甲だけ。
・足幅は骨盤幅か大転子幅程度に開く。
アップドッグではいきなり腰椎を反り過ぎると腰を痛めます。なので腹横筋と腹直筋を使い腰の反りにブレーキをかけながは胸椎を反っていきましょう。膝を床から浮かせるのがきつい場合には膝をついたコブラのポーズから練習すると良いかもしれません。胸椎の反りのみを練習したい場合にはRSYのクラスでもよく行っているベビーコブラ(みぞおちから下を全部床につく)から始めてもいいと思います。
後屈は体の前面が伸びているので一見お腹を使ってなさそうですが、腰を痛めないためにはお腹の使い方が大事になります。アナ骨のローランジ後屈(ジラフ)などと共にお腹の使い方(骨盤後傾方向の力)を覚えていきましょう。
熱中症
2019/08/09
こんにちは。このブログでも毎日の猛暑に「暑さに気をつけてください。」なんて呼びかけておいて、昨日は僕自身が熱中症気味になってしまいました。。
昨日はiプラザへの自転車移動や水泳のパーソナルレッスンのための移動などで太陽の下を歩く時間が長かったのですが、もともと汗のかきやすい体質、水分や塩分補給が間に合わなかったのでしょう。鈍い頭痛と気持ち悪さが出てしまいました。
これはまずいと思い家に帰ってから塩とレモンを混ぜた水をしっかり摂り、少し落ち着いた後に子供達用に作ってあったみそ汁の汁だけを何杯か飲みました。するとずいぶんと頭痛や吐き気は収まり夜の水泳レッスンにも行くことができました。
ただやはり一度水分や電解質を体外に出し過ぎてしまうとすぐには元の状態までは回復しないようで今日もだるさが少し残っています。調子が落ちる前の水分補給の大切さを改めて実感しました。
今はOS1のような経口補水液など体への吸収の良い製品もたくさん売られています。汗をたくさんかくような場面ではそういった物も活用しながら体調管理をしてみてくださいね。
Carry Ribbon
2019/08/08
こんにちは。相変わらずの暑さですね。大量に汗をかくのにも慣れてしまいました。
ところで一週間ほど前に名前の募集を開始した若葉台iプラザ用のミニ骨格標本ですが、おかげさまで名前が決定しました。
その名は、
キャリボン。
考えてくれた方によると、矢野口のスタジオにいる等身大骨格標本のリボンちゃんのリボンに持ち運びができるという意味でキャリー"carry“をつけたそうです。リボンちゃんとの姉妹感も出ているのでこの名前に決定しました。
この他にもたくさんの名前の候補をいただきありがとうございました。また何か名前をつける時にはご協力いただけたら嬉しいです。
ちなみにうちの長男(3歳)は家にあるミニ骨格標本のことをいつのまにか「ガリ蔵」と呼んでいました。確かに肋骨が薄かったり痩せ型の体型ではあるので間違ってはいない感じです。子供のセンスは恐ろしい…
では明日明後日はともにアナトミック骨盤ヨガです。夏に負けない体づくりをしていきましょうね。
立ち位置を変える
2019/08/07
一週間ほど前のブログで「診る力」について書きました。→103回目〜「診る力」〜
そして一週間前の水曜夜には「診る力」をつけるためのグループワークをレッスンの冒頭に行いました。三人一組のグループに分かれて、そのうちの1人が他の2人のアーサナの誘導を行うというもの。つまりインストラクター側の目線に立ってもらったのです。
行ったアーサナはヴィーラバトラアーサナII(ウォリアー2)、ウッティタ・トリコナーサナ(三角のポーズ)、パリヴルッタ・トリコナーサナ(ねじりの三角のポーズ)の3種類。自分の覚えていることを、どんな言葉でどんな順序でもいいので他のメンバーに伝えてアーサナを導きます。
参加者の間からは「思ったより難しい!」「このポーズは骨盤がどの向きだっけ…?」「なんとなくポーズは覚えているけどどこを意識したらいいかわからない…」など色々な声があがりました。
普段のレッスンでは情報を受け取って実践するのみとなりますが、このように情報を整理して発信する側に立つことで気づくこともあったようです。
自分は何が本当にわかっていて何がわかっていないのか?
自分の今の位置がわかるとまた新たにその場所からスタートできます。たまには立ち位置を変えてみることも良い刺激になったのではないでしょうか。(と勝手に思っています。)
なかなか効果があったと(勝手に)思っているので今日の夜のレッスンでもまた違うアーサナで試してみようかなと思います。他の曜日でも様子を見て実践していこうと思います。
仙骨
2019/08/06
昨日は首の後ろを温める方法を紹介しましたが、あと一つ、温めると効果的な場所があります。
それは、
仙骨(写真はまだ名無しのミニ骨格標本のものなので形がいびつです…)。
仙骨はお尻の真ん中、左右の骨盤をつなぐ位置にある骨。尾骨と、腰椎の間にあります。仙骨は血流や神経の要所と言われています。ここを温めると全身の血流が良くなり、副交感神経が優位になるそうです。
リラックスしたくてもできなかったり、寝付けない時などに仙骨を温めると効果を感じられると思います。温める方法は首の後ろと同じでどんな方法でも良いと思います。湯たんぽを使ったり、温かいシャワーを浴びたり。物を用意する元気もない時は手を仙骨に当てるだけでもだいぶ調子が変わることもあります。
整体などでは仙骨から腰痛にアプローチすることもあるくらいなので、腰の痛い方もぜひ温めたい部分となります。
首の後ろと合わせてこちらもぜひお試しくださいね。
首の後ろを温める
2019/08/05
昨日は夏場の暑さと腰痛の関係などについて軽く触れましたが、今日は腰痛や肩こりや疲労に効く一つの方法を紹介します。
昔からありふれた方法ですが抜群に効果があります。それは、
首の後ろを温めること。
首の後ろを温めることで全身の血行が良くなりリラックス効果、疲労回復効果などが期待できます。特に今は冷房で首元が冷えてしまっている方も多いと思うので、一日一回でも温めてあげると身体をリセットできます。
タオルを濡らしてレンジでチンしたり、湯たんぽを使ったりと、方法はなんでも良いですが、10〜20分温めると効果を感じられると思います。あとは首の後ろを温めるための商品なんかも出ています。僕もちょうど5年前に受験勉強を始めた時にあずきの蒸気で首元を温めるような物を使っていました。机に向かって目線を落とし首に負担をかけながら勉強していた頃に体を元気にする効果があったのを覚えています。
この暑い夏に温めるなんて…と思うかもしれませんが、気づかない間に体を冷やしてしまう夏にこそ必要なのではないかと思います。(冬は冬で同じことを言っているかもしれませんが…)
簡単にできることなので不調を感じている方はぜひ試してみてくださいね。
暑さとギックリ腰
2019/08/04
こんにちは。
最近はなんだか体調を崩す人が増えているように思います。長く続いた梅雨から急激な猛暑、身体には相当な負担がかかりますね。
特に増えているのがギックリ腰を始めとした腰痛。夏の暑さで冷たいものを多く飲んだり食べたりしていると内臓が冷えて機能が落ちます。そしてお腹周りが硬くなることで腰を支える力がうまく働かなくなりギックリ腰になったり慢性の腰痛が悪化したりします。夏の冷えは盲点かもしれません。なるべくお腹を冷やさないように過ごしたいものですね。
具体的な対策としては冷たいものを食べすぎないこと、クーラーで首や腰を冷やしすぎない、適度に塩分を補給する、適度な運動をする、などでしょうか。
自分の生活スタイルに合わせた対策をして元気に夏を乗り切っていきましょう!
セミ
2019/08/03
昨日の夜仕事が終わって家に帰ると3歳の長男が珍しくまだ起きていました。何事かと思ったらセミの幼虫をつかまえたのを僕に見せたかった様子。どうせならと思い息子と一緒にセミの羽化まで観察することにしました。
どこか幼虫がとまりやすく、なおかつ観察しやすい場所はないかなと家の中を見回してみると、お風呂場がその条件に一番合っているようでした。早速浴室の網戸にセミ幼虫をつかまらせると上の方まで移動していって動きを止めました。あとは羽化が始まるまで待つだけです。
結局ちょうど一時間後に羽化が始まり、背中が割れて中から綺麗な色(薄緑&白)の成虫が出てくるのを息子と一緒に観察できました。息子はいつもはとっくに眠っている時間ですが眠さを抑えて最後まで起きていました。
僕も最近は早朝アシュタンガヨガを行っているので夜も22時半には寝る生活を送っていました。なので23時を過ぎると眠さの限界を超えていました。前は1時頃まで起きていた生活だったのに習慣というのはすごいものだなと感じました。
なんにしても夏休みらしい一夜でした。
朝食
2019/08/02
今日も暑いですね、というのが最近の挨拶です。「おはようございます」よりも頻繁に使っているかもしれません。
今日はここ半年ほど気に入っている朝食を紹介したいと思います。それは、
ミューズリー 。
知っている人は知っているし、知らない人は知らないと思います。(←当たり前ですが。)ドイツなどでは当たり前に朝食などに出てきます。
どんなものかと言うと、鳥のエサみたいなものでシリアルの一種ですね。似ているものとしてグラノーラがありますが、ミューズリーはグラノーラとは違い砂糖など糖分の添加がなく、穀物(オート麦や大麦など)もそのまま潰された形で入っています。(たまに砂糖など添加されていてもミューズリーとして売っていたりもします。)
僕が近くのスーパーで買っているものには、穀物にナッツやドライフルーツが加えてあります。そのミューズリーに豆乳やヨーグルトをかけて、時にはバナナを加えて食べています。食べ方は好みによって色々と変えられると思います。
個人的に思うミューズリーの利点は以下のようなこと。
・糖分(砂糖など)の添加がないので血糖値の急な上昇や下降がない。
・食物繊維が豊富でお腹の調子がとにかく良くなる。
・良く噛まないと食べられないので、顎や頭の筋肉が動き脳への血流アップ+小顔効果。
僕自身、糖分の代謝がけっこう苦手なところがあるので、砂糖たっぷりのグラノーラだと若干調子が崩れます。個人の感想ですがミューズリーだと血糖値の不安定さを感じません。
そして一番効果を感じるのは便の質が驚くほど良くなること。そもそも便秘ではありませんが、ミューズリーを食べている時は、なんというか、良質になります笑
あとはダイエットしたい方には合っている食べ物なのだと思います。カロリーが少なく栄養豊富で腹持ちが良く、便の調子が良くなるので、朝食のパンの代わりにでも食べれば効果は得られるかもしれません。運動ありきだとは思いますが。
色々と良いことを書きましたが、もちろん小麦アレルギーやセリアック病の人などには向きません。それに人によって食べ物の向き不向きはだいぶ違います。食べた後に眠気やだるさがあるものは体質に合っていないか量が間違っている可能性があります。なんにしても腹7〜8分目に抑えておくと余計な負担を体にかけず集中力も持続します。
体に悩みがある人は食についても見直してみると思わぬ発見があるかもしれません。
ミニ標本
2019/08/01
少し前に始めたiプラザでのアナトミック骨盤ヨガのレッスンのために実は小さな骨格標本(40cmほど)を導入しました。スタジオLinoに置かせてもらっている骨格標本のリボンちゃんは等身大サイズで作りもしっかりしていますが、iプラザへ持ち運ぶために購入した標本はなんとも言えない作りです。
肋骨がやけに薄っぺらかったり、頭蓋骨が長かったり。。でもやはり骨や筋肉の説明をする時には骨格標本があるとわかりやすく、小さくても活躍しています。
ただ今日ふと気付いたのはこのミニ骨格標本にはまだ名前がないこと。等身大のリボンちゃんよりは活躍の場が少なく存在感が薄いですが、名前はあったほうがいいのかなと思います。
ということでこの写真の標本の名前を募集します。期間は今日から一週間くらいにします。
もし何か思いついた方は直接でもメールでもアイデアをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
明日、明後日はアナトミック骨盤ヨガですね。骨盤力をつけていきましょう!
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










