- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
マイソールクラス
2019/06/30
ローランジ・補足
2019/06/29
ローランジはアナトミック骨盤ヨガで頻繁に登場しますが、レッスン中動きを見ていますと首の動きが気になることがあります。疲れてくると頭が床の方に落ちて首が丸まってしまったり目線を上げ過ぎて首の反りが強くなってしまったりします。
ローランジでは背骨のカーブを通常立っている時と同じ状態(生理的弯曲)に保ちます。首が丸まってしまうと背中や腰も丸まりやすくなり、逆に首が反り過ぎてしまうと目線だけが上がって腰や背中の意識が抜けてしまいます。
ですので立ち姿勢で前を見ている時と同じように首の後ろ側はまっすぐに保ちます。ローランジの場合、上半身は斜めに保った状態ですので目線は斜め前の床の方に向かいます。目線が足元に落ち過ぎていたり首の後ろにシワができている場合などは、首が丸まったり反ったりしている状態かもしれません。
慣れないうちは下半身の土台をつくるので精一杯かもしれませんが、だんだんと背骨の使い方の意識も持てるようになるとアーサナの質も上がります。
急には難しいかもしれませんが一つ一つ出来ることを積み上げて練習してみてください。
アーサナメモvol.3
ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ(ローランジ)
2019/06/28

タイムリミット
2019/06/27
制限時間
2019/06/26
集中しやすい場所
2019/06/25
極楽鳥
2019/06/24
羽化
2019/06/23
遅筋と毛細血管
2019/06/22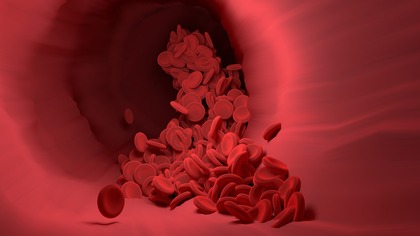
遅筋と速筋
2019/06/21
冷え
2019/06/20
写真撮影
2019/06/19
アナ骨@若葉台iプラザ
2019/06/18
蝶と蛾
2019/06/17
アーサナメモvol.2
タダアーサナ
2019/06/16

前後開脚〜ハヌマーンアーサナ〜
2019/06/15
ですので前後開脚のための要素はアナ骨をやるだけでも揃ってきます。またただのストレッチとは異なるのは、自分の身体の内側から熱を発することで筋肉も無理なく伸びること。熱がない状態の無理なストレッチは筋肉を痛めやすいのです。
そんな感じで股関節の柔軟性アップにも効果のあるアナ骨ですが、レッスン後に先ほどのS君が前後開脚を試してみると、べったりお尻が床についていました。(あとはこれを繰り返していけば骨盤が完全に正面を向いて立った状態にまでなってくると思います。)他の参加者の方も試していましたが、レッスンが始まる前とは別次元の開き方をしていました。そもそも前後開脚自体やったことのない方もかなりいい所まで開けていたように思います。
ちなみに前後開脚はヨガでは"ハヌマーンアーサナ"「猿神のポーズ」という名前がついていて、インドの神話に登場するハヌマーンを模したアーサナです。なんだか名前もかっこいいですね。
身体の使い方がわかるとできるようになるアーサナですので、挑戦してみたい方はポイントをおさえてコツコツと材料をそろえてみてください。
金曜アナ骨
2019/06/14
日課
2019/06/13
三沢川
2019/06/12
アーサナメモvol.1
アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナ
2019/06/11

さなぎ
2019/06/10
教えるのか、シェアするのか
2019/06/09
骨盤前傾
2019/06/08
ベターかベストか
2019/06/07
優先順位
2019/06/06
絶対的規範
2019/06/05
「ら」抜き言葉〜その2〜
2019/06/04
「ら」抜き言葉
2019/06/03
後屈のポイント〜上半身編〜
2019/06/02昨日はローランジからの後屈の下半身のポイントをお伝えしましたが、今日は上半身の使い方です。
後屈のポイント〜土台編〜
2019/06/01昨日の「ら」抜き言葉の続きはまた今度書きますが、今日は今朝のアナトミック骨盤ヨガで練習した後屈についてです。
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










